マルナス助手に頼まれ、『AI未来予想VR装置』を体験中のネギーン。
AI(人工知能)が予想した、ネギーンの7年後の未来・・・それは、ネギーンが想像していたような『自分に合った友達』に恵まれた楽しい高校生活・・・ではありませんでした。
ネギーン「(なんか僕、また笑われています・・・。みんなからバカにされているみたいで、辛いです・・・。)」
ネギーンの遠慮がちな性格は小学校の頃から変わっていませんでした。
人に嫌なことを言われても、嫌だと伝えられず、ずっと黙っていました。

特に、ネギーンが苦手に思っているのはクロマメオでした。
クロマメオは、グループの中でひときわ存在感があり、いつも鋭い言葉でネギーンをイジってきました。
そして、その『イジり』に常に同調するスモモビーとメロ太。
しかし、ネギーンは知っていました。よくよくこのグループを冷静に見ると、スモモビーも、メロ太も、常に、クロマメオの機嫌を伺って、話を合わせているだけだったのです。
ネギーンが他のことを考えていると、すかさず、クロマメオが話題を切り込んできました。
クロマメオ「ネギってさ、勉強の成績はいいけど、頭の回転は悪いタイプだよな〜。」
スモモビー「そ、それ言うw鬼w」
メロ太「ネギちゃん傷つくわ〜w」
ネギーン「そ、そうなんですよぉ。クロマメオ君みたいに地頭(じあたま)がいい訳ではないから、羨ましいです!(またクロマメオ君に調子を合わせるだけの時間・・・とても退屈ですぅ。)」
クロマメオ「いいか、ネギ!俺との会話で地頭を鍛える練習した方がいいぞ。これ本気でwお笑いトーク番組を見て『返し』を学べ!」
・・・
クロマメオはよく、上手い言葉の『返し』方を友達に要求してきました。
ネギーンはもうウンザリしていました。
クロマメオは人に対する圧も強く、やたらおせっかいなところがありました。生まれつき頭の回転がいい上、目立ちたがり屋で、負けず嫌いの努力家でもありました。
おそらくスモモビーもメロ太も、そんなクロマメオといることにウンザリする時間もあったでしょうが、なんせこの高校生活、誰もひとりぼっちにはなりたくありません。
無理してでも友達?を作らないと、学校にいる間は孤独になってしまいますし、男の子は女の子にも相手にしてもらえません。
思いもよらない厳しい環境だったネギーンの高校生活・・・。
そして退屈な休み時間は終わり、次は体育の授業の時間になりました。
ネギーン「(ふぅ・・・。今日の授業はグラウンドに移動してマラソンです。走って一汗(ひとあせ)かいてスッキリしましょう!)」
ネギーンは体操着に着替え、校庭のグラウンドへと向かいました・・・が、
ネギーン「(あ、、、制汗剤(せいかんざい)付けるの忘れちゃいました・・・。)」
みんなは制汗剤を知っていますか?
汗をかいたときに、においを防止するスプレーのことです。
ネギーン「やれやれ、制汗剤を忘れて汗くさいままだったら女の子から嫌われちゃいます・・・それに、クロマメオにまたイジられたら・・・。」
ネギーンはそんなことを思いながら、制汗剤を取りに、1人教室へと戻りました。
すると、そこには・・・

ネギーン「(え、、、パプリカの、パプリリカさんだ・・・。)」
ネギーンはとてもビックリしました。
体育の授業が始まるというのに、着替えず、1人だけ教室に残って、本を読んでいる女の子がいたのです。
ネギーン「き、君、、、つ、次は、体育の時間ですよ・・・!」
パプリリカさんはネギーンが教室に戻ってきたことに気づき、頭を上げ、ネギーンの方に目線を向けました。
ネギーン「た、たしか女子は、体育館に移動するのではなかったでしょうか・・・?」
普段、あまり女の子と話すことのなかったネギーン。けれど、心配になり、思い切って話しかけます。
パプリリカ「・・・知ってるよ。でも、私、行かないの。気にしないで、放っておいてね。」
ネギーン「し、しかし・・・。」
パプリリカさんは返事をしてくれましたが、ネギーンは様子がおかしいと察しました。
パプリリカさんはただ授業をサボろうとしている訳ではなく、何か事情があるようです。
ネギーン「具合が悪いんですか・・・?そしたら、保健室に行くか、先生に言って早退した方が・・・。」
ネギーンは勇気を出して、もう少し話しかけてみました。
パプリリカ「元気よ。全然、体調もいいわ。でも、私、行かないの。」
ネギーン「げ、元気なんですね・・・!それなら、とりあえず、よかったです!」
元気と答えたパプリリカさんに、ひとまず安心したネギーン。
パプリリカさんは、そのホッとしたネギーンの表情を見て、目を丸くして驚いていました。そしてこう言いました。
パプリリカ「ネギくん、私のこと、心配してくれたの?ありがとう・・・。」
パプリリカさんはネギーンにお礼を言うと、今度は、視線を少しそらしながら、続けて言いました。
パプリリカ「私、このクラスに、いないことになってるから。心配してくれたの、ネギーンくんだけよ。」

パプリリカさんは、少しギャルっぽくて、かわいい女の子でした。化粧も濃いめで、このクラスの女の子の中では目立つ存在でした。
同じクラスになって半年が経ちましたが、ネギーンはこの日、この瞬間、彼女と初めて会話をしました。
ネギーン「いないこと?になってるって、、、どういうことですか?」
パプリリカ「私ね、このクラスの女子全員から無視されてるの。」
ネギーン「え!」
パプリリカ「気づいてたでしょ?」
ネギーン「いえ、ぜんぜん気づきませんでした・・・。そんなことがあったんですね。それで、体育の授業を・・・?」
パプリリカ「そうよ、今日はダンスの授業なんだけど、自由にグループを組んで三学期の最後の授業で発表するの。でもね、私、誰ともグループを組んでもらえなかったの。私だけ、1人で踊らなければならないの。練習するときも。発表会の当日も。私以外のみんなは4、5人でグループを組んでいるわ。それなのに、私は、1人・・・。」
事情を話しながら、少し声が震えているパプリリカさん・・・。
ネギーン「それは、辛すぎますね・・・。先生には相談はしたんですか?」
と、ネギーンは途中まで言いかけて
ネギーン「・・・あ、先生になんて、言えないですよね。お父さん、お母さんにも、心配かけちゃうから、言いにくいですよね。その気持ち、僕にもわかります・・・。」
気遣う言葉をかけてくれたネギーンに、パプリリカさんは少しだけ安心したような表情を見せました。
パプリリカ「同情してくれて、ありがとう。このことは、先生も知ってるのよ。でも、何もしてくれないわ。ここは進学校だから、勉強の成績さえ良ければ、先生たちはそれでいいのよ。」
ネギーン「そ、そうなんですか・・・。」
そう言いながら、ネギーンは自分が体育の時間に遅れそうなことを思い出し、ソワソワし始めました。
ネギーン「(どうしよう、早く行かないと・・・。でも、パプリリカさんをこのまま1人にしていいのでしょうか?)」
そしてネギーンは、ふと、昔友達だった『あの子』のことを思い出しました。
ネギーン「(こんなとき、『あの子』だったらどうするでしょうか・・・?)」
ネギーンの頭に浮かんだ『あの子』・・・それは、『クリビー』でした。
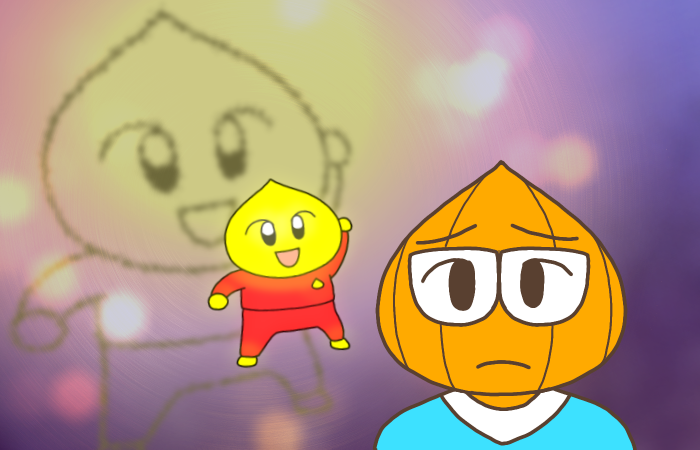
ネギーン「(こんなとき、もし僕が『クリビー』だったら、どうするんだろう?『クリビー』なら、授業に遅れるのなんか気にしないで、いま目の前で悲しんでいるパプリリカちゃんの気持ちに寄り添ってあげるんじゃないですか・・・?)」
ネギーンは心の中で自問自答(じもんじとう)をしました。自問自答とは、自分で質問して、自分で答えるという意味です。
そして、ネギーンは心の中で、答えを決めました。
ネギーン「あの、パプリリカさん、僕でよかったら友達になりましょう。」
ネギーンはシンプルに、そう言いました。
つづく

